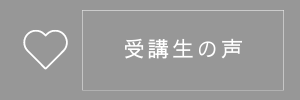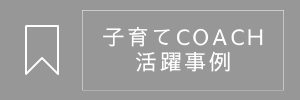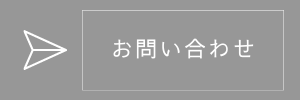皆さまこんにちは!CPIの宇田川です。
あなたのお子さんは自己肯定感が高いですか?それとも低いですか?
今回は2回に渡ってお送りしていきます。
自己肯定感とは?
思春期の子どもが自分に自信を持ち、困難を乗り越えるための最強の武器。
それが「自己肯定感」であり、
「自分はありのままで価値のある存在だ」と感じる気持ちのことです。
この感覚がしっかりしていると、子どもは…
・他人の評価に左右されず、自分の意見を言える。
・失敗を恐れずに新しいことに挑戦できる。
・将来の目標に向かって、自分で考えて行動できる。
逆に、自己肯定感が低いと…
・「どうせ僕/私には無理だ…」と、やる前からあきらめてしまう。
・人の顔色ばかりうかがい、自分の意見を言えなくなる。
・必要以上に自分を責めてしまい、自信をなくす。
『どうせ俺なんて、私なんて・・・』という言葉がでてきたら要注意です。
思春期に響かないNGワードの正体
私たちは、子どもが失敗したり、言うことを聞かなかったりすると、
ついこんな言葉をかけてしまいます。
「何度言ったらわかるの!」
「どうせお前には無理だ」
「みんなはできてるのに、なんで…」
これらの言葉は、子どもの行動を責めているように見えますが、
実はその裏に隠されているのは、親自身の「将来への不安」や「イライラ」です。
思春期の子どもは、親の言葉の奥にある「本音」を敏感に察知します。
「どうせ僕の気持ちなんて分かってくれない…」
「また否定された…」
そう感じた子どもは、心を閉ざし、自己肯定感を大きく傷つけてしまいます。
条件付きの愛情が子どもの自己肯定感を奪う
あなたのお子さんが100点をとってきたとしましょう。
あなたはどのように褒めますか?
たとえば「100点を取ってすごいね」と褒めたとします。
一見当たり前に褒めているように思えますが、結果だけを褒めることによって子どもは
『100点を取る自分は褒められるけど、100点を取れない自分には価値がない』
というメッセージを同時に受け取ります。
では、どうしたらよいのでしょう?
100点を取るまでに、
どれだけ努力をしたかプロセス(過程)を褒めることが大切になります。
「今回は前から計画を立てて、勉強してからゲームをやっていたよね。その頑張りが凄いと思うよ」
など、このようにプロセスを褒める習慣は
たとえ結果が出なかった時も、親は自分のことを分かってくれていると安心します。
大事なのは子どもの状態をよく見て結果だけを褒めるのではなく、
そこに至るプロセスを伝えて褒める事です。
究極のOKワード「存在承認」
思春期の子どもは、テストの点数や部活の成績、友達との関係など様々なことで
「自分の価値」を測ろうとします。
しかし、究極の自己肯定感は、
「何もしていなくても、ただそこにいるだけで価値がある」
と感じられることで育まれます。それが「存在承認」です。
子どもが、
「自分はどんな状態でも愛されている」「かけがえのない存在なんだ」
と思えるように、
「生まれてきてくれてありがとう」「あなたはかけがえのない存在」
という言葉やメッセージ、「存在承認」の言葉を、折に触れて伝えてあげてください。
この言葉こそが、思春期という不安定な時期を支える揺るぎない心の土台になります。
次回はNGワードをOKワードに変えていくための具体的方法をお伝えします。
(執筆:宇田川昌子COACH)
外部リンク:ホームページ https://cpi-x.com/
コーチングのコミュニケーションで
子どもの成長を支え、子どもを導く親になる!
NLP子育てCOACH™無料体験会を開催中!
体験会では、あなたの課題や問題を整理し、
自分の子育ての軸をみつけることができます!
この機会にぜひ参加してみませんか?
〜子育てに悩んでいませんか?〜
子育ての悩み相談はこちらから
NLP子育てCOACHトレーナーが相談にのります
ちょっとしたことから深い悩みまで
何でもご相談ください♬

カウンセラー/コーチ 宇田川 昌子
・NLPマスタートレーナー
・CPI教育研修部マネージャー
私立中学や教育現場で保護者や先生を対象に講演やセミナーの実績多数。常に現場で保護者の悩みを聴きカウンセリングやコーチング等様々なサポートを行っている。自身の息子の不登校を克服した経験ももつ。