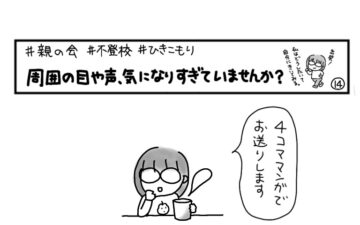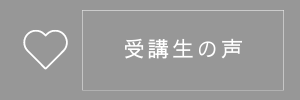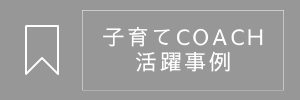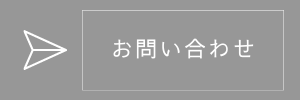子育てフォーラムレポート:
「学校に行かない子ども達〜医学の観点から 敏感さと起立性調節障害の子どもの母として伝えたいこと~」
当日はオンライン参加の皆さんと一緒に、私も一人の保護者として深く学び、考える時間になりました。
講師の樋口先生からは、現在の不登校の状況について具体的なデータをもとにお話しいただきました。小学生では60人に1人、中学生では17人に1人が不登校という調査結果からは、不登校は特別なことではなく、誰にでも起こりうることであるということ。そして、そこには「登校したくてもできない」さまざまな背景があるということを、参加者の皆さんと一緒に理解することができました。
体の不調として多く見られるのが「起立性調節障害(OD)」です。自律神経の働きがうまくいかず、朝起きづらい、立ちくらみがする、倦怠感があるといった症状が出ます。これは「怠け」や「甘え」とは異なるものであり、体の仕組みによるものです。このことを知っているかどうかで、子どもへの声かけや接し方は大きく変わってくると感じました。
また、発達の特性や感覚の敏感さ(HSP)の傾向をもつ子どもたちが、不登校になることもあります。「みんなと同じように」が難しい子どもにとって、集団生活は大きな負担になることもあり、子どもの立場からすれば、苦しいのは「行かないこと」ではなく、「無理をして行こうとすること」かもしれません。そうした視点を私たち大人が持てるかどうかが、子どもとの信頼関係にもつながっていくのだと思います。
そして、不登校状態の生徒が増加する思春期についてのお話もありました。思春期は、子どもが自分の価値観を築き始める大切な時期です。親や周囲との距離感に揺れながら、自分らしさを模索しています。大人ができることは、無理に方向づけたり急がせたりすることではなく、見守ること、待つこと、そして必要なときに手を差し伸べること。それは簡単ではありませんが、樋口先生が紹介された「北風と太陽」の話は、私たちにとって大きなヒントになりました。
さらに、親の立場での体験談からは、共依存という関係のことや、日々の出来事に丁寧に向き合い、親自身が変わっていくことの大切さ、不登校を心配しすぎることは、親の問題であることが語られ、多くの共感が集まりました。
今回のフォーラムは、不登校を「問題」としてではなく、「子どもからのサイン」として捉えるきっかけになったのではないかと思います。私自身も、子どもの姿を一歩引いて観察する大切さを感じました。
今後も、保護者の皆さんとともに学び合える場をつくっていきたいと考えています。
ご参加くださった皆さま、本当にありがとうございました。

(レポートby 子育てcoach 鈴木友子)