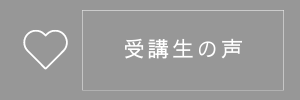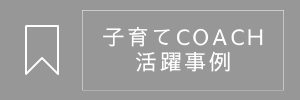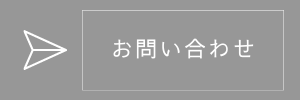皆さまこんにちは!CPIの宇田川です。
今回は『普通って何?朝になると起きられないって怠けている?』
というテーマでお送りします。
息子が不登校になった時、なかなか朝起きない息子に対して
『多くは望まないので、普通であってくれればいい』と思っていました。
その時の私にとって、子どもは普通に朝おきて、普通に学校に行って、
普通に学校生活を楽しんでくれれば他に望むことはないという感じでした。
あなたにとって『普通』とはどんな状態でしょうか?
皆さんも無意識に『普通』という言葉を使っていませんか?
『普通』の呪縛から抜け出す
私たちは無意識のうちに「普通」という基準で物事を判断しがちです。
「みんなはできているのに、なぜうちの子だけ?」
「ここでしっかりさせないと大変なことになる」
等、そんな思いが、子どもをさらに追い詰めます。
得意なことも、苦手なことも、心と体の状態も、人それぞれです。
「普通」は、あくまでたくさんの人の平均値。
子どもがその平均から外れているからといって、
人格否定をしてはいけません。その「朝起きられない」という行動の裏には、
怠けとは違う、もっと深刻な原因が隠されているかもしれません。
起立性調節障害(OD)をご存じですか?
朝起きられない原因の一つに、
起立性調節障害(OD)というものがあります。
これは、自律神経の働きに問題が生じ、
立ち上がった時に脳や全身への血流がうまくいかなくなり、
以下のような症状が現れます。
・朝、起きられない
・立ちくらみやめまい
・倦怠感、集中力の低下
・食欲不振や腹痛、頭痛
午後になると元気になるため、怠けていると思われがちですが
これらの症状は、怠けや甘えではなく、
医学的な原因があり「体のSOS」といえるかもしれません。
親にできることは?
・子どもの話に耳を傾ける→ 否定せずにどんな話でも最後まで話を聴く
体の不調を訴えていないか、学校生活で悩んでいることはないか等です。
やってはいけない事は学校に行かせるために誘導することです。
ニュートラルに話を聴きましょう。
・子どもの不安に「大丈夫」と安心させる
無理に登校を促すのではなく、「今はつらいんだね、大丈夫だよ」
と寄り添うことがお子さんにとって最大の安心になります。
・専門機関に相談する
起きる時間や寝る時間等様々工夫したり試しても改善しない場合には
小児科や心療内科など、専門の医師に相談することも大切です。
適切な診断と治療で、症状が改善する可能性があるからです。
起立性調節障害の子どもの「朝起きられない」という行動は、
子どもの体が必死に発している「心のSOS」なのです。
その『心の声』を聴き取り
親として、そのサインを見逃さず適切な対応をしていけるとよいですね。
弊社では「子育てフォーラム」という、
年に一度(毎年7月初旬開催)の勉強会があり、
今年度は小児科医でもあり、起立性調節障害のお子さんを育てられた
新大久保にじいろおやこクリニックの樋口麻子先生をお招きして、
医学の観点から、そして親の観点から
不登校につながる起立性調節障害についても学びを深めました。
うまく付き合って、症状を軽くしていくのかが大切で、
その中でも親子のコミュニケーションが重要だとおっしゃっていました。
「学校に行かない子ども達
~医学の観点から敏感さと起立性調節障害の子どもの母として伝えたいこと~」
思春期をうまく乗り越えるために皆様を応援しています!
次回は『不登校、行き渋りに悩む親がしっておきたい『待つ力』です♪
(執筆:宇田川昌子COACH)
外部リンク:ホームページ https://cpi-x.com/
コーチングのコミュニケーションで
子どもの成長を支え、子どもを導く親になる!
NLP子育てCOACH™無料体験会を開催中!
体験会では、あなたの課題や問題を整理し、
自分の子育ての軸をみつけることができます!
この機会にぜひ参加してみませんか?
〜子育てに悩んでいませんか?〜
子育ての悩み相談はこちらから
NLP子育てCOACHトレーナーが相談にのります
ちょっとしたことから深い悩みまで
何でもご相談ください♬

カウンセラー/コーチ 宇田川 昌子
・NLPマスタートレーナー
・CPI教育研修部マネージャー
私立中学や教育現場で保護者や先生を対象に講演やセミナーの実績多数。常に現場で保護者の悩みを聴きカウンセリングやコーチング等様々なサポートを行っている。自身の息子の不登校を克服した経験ももつ。